老後2000万円問題とは?
「老後2000万円問題」とは、2019年6月に金融庁がまとめた報告書(『高齢社会における資産形成・管理』)の中で示された試算をきっかけに話題となった問題です。
簡単に言えば、
『夫婦が65歳で定年退職を迎え、その後30年間(95歳まで)年金だけに頼って生活を送る場合、約2000万円の貯蓄が必要になる』
という内容で、多くのメディアで取り上げられ、国民的な関心事となりました。
問題になった経緯
- 金融庁報告書の内容
- 報告書によると、夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)の無職世帯では、毎月の平均収支が約5万円の赤字になるとされています。
- 仮に95歳まで生きると想定すると、5万円×12ヶ月×30年=約1800万円の不足(約2000万円の蓄え)が必要になる、という計算でした。
- 「年金制度の破綻」をイメージする人が増加し、老後の生活への不安が広がり、政治的な論争を呼び、当時の国会でも議論されました。
なぜ2000万円不足すると言われたのか?
金融庁が試算に使ったデータは次のとおりです:
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 収入(主に年金) | 約21万円 |
| 支出 | 約26万円 |
| 毎月不足額 | 約5万円 |
公的年金の具体的な内訳
一般的なモデルケース(夫婦二人の標準的なケース)の年金額を参考にすると、次のようになります。
- 夫の年金(厚生年金+国民年金)
- 平均的なサラリーマンとして40年間勤続した場合:月額約14~16万円
- 妻の年金(主に国民年金)
- 専業主婦やパート勤務の場合:月額約5~6万円
夫婦合算で、だいたい20~22万円程度が平均的です。この報告書では、それを切りよく「約21万円」としています。
重要な注意点
- この金額はあくまで平均値であり、実際には勤続年数、収入水準、加入していた年金制度(厚生年金か国民年金か)によって大きく異なります。
- 自営業者(国民年金のみの場合)は、夫婦合算でも10万円前後になるケースが多く、この報告書のモデルケース(会社員世帯)よりもさらに収入は少なくなります。
国民年金のみの場合の収入例(月額)
国民年金の支給額は以下のとおりです(2023年度)。
- 満額受給額(40年間保険料を納めた場合)
- 月額:約6.6万円(年額約80万円)/1人あたり
- 夫婦二人の場合:合計約13.2万円
つまり、自営業者の場合は、厚生年金をもらえる夫婦世帯(約21万円)と比べて、約8万円ほど収入が少なくなります。
| 年金制度 | 夫婦合計月額(目安) |
|---|---|
| 厚生年金+国民年金 | 約20~22万円 |
| 国民年金のみ | 約13万円前後 |
月々の不足額はいくらになる?
金融庁が示した平均支出(夫婦で約26万円)を前提にすると、自営業者世帯の場合は次のようになります。
| 項目 | 自営業者世帯(月額) |
|---|---|
| 収入(国民年金のみ) | 約13万円 |
| 支出(一般的平均) | 約26万円 |
| 毎月不足額 | 約13万円 |
毎月約13万円の不足が生じるため、30年間(65歳〜95歳)にわたり必要な貯蓄額は次の通りです。
13万円×12か月×30年=約4680万円
つまり、自営業者の場合、いわゆる「2000万円問題」どころではなく、約4700万円近くの貯蓄が必要になる可能性があります。
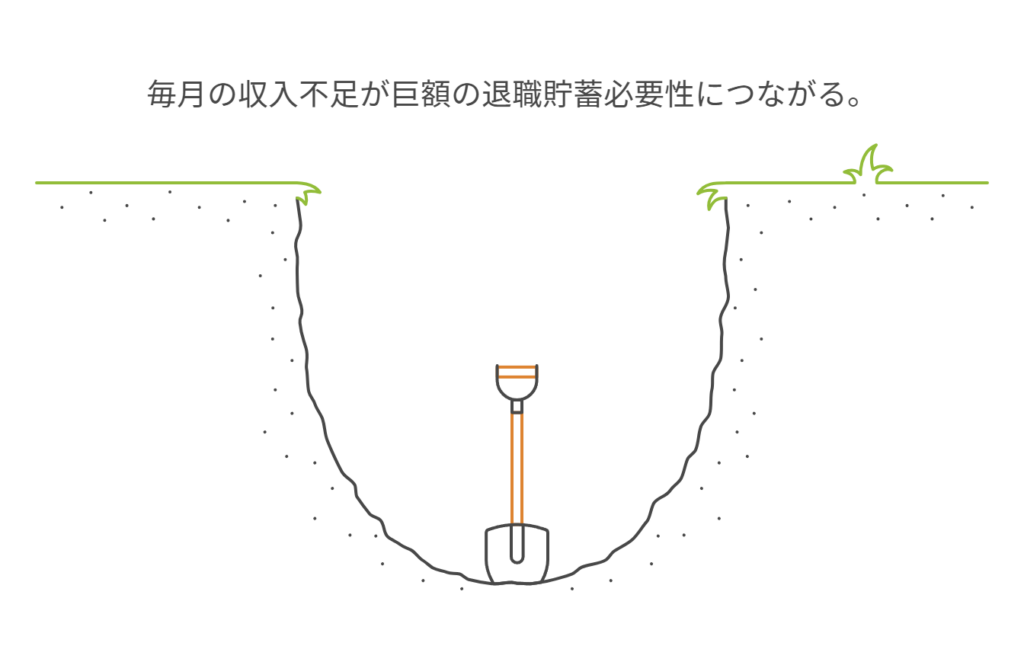
誤解されやすいポイント
「2000万円必要」というのはあくまで一例であり、すべての人に当てはまるわけではありません。各家庭や個人の状況により、必要な老後資金は異なります。
また、報告書は「年金制度が破綻する」という内容ではなく、「年金以外に個人でも資産形成をする必要がある」という趣旨で書かれています。
対策としてできることは?
以下のような対策が推奨されています。
- 個人での資産形成
- つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの税制優遇制度を活用した投資や貯蓄を行う。
- 長期的なライフプラン設計
- 自分の老後に必要な金額を具体的に見積もり、長期的な視点で貯蓄や投資の計画を立てる。
- 働き方の見直し
- 定年を延ばす、再就職、パートやアルバイトをするなど、収入を確保するために老後の働き方を柔軟に検討する。





コメント